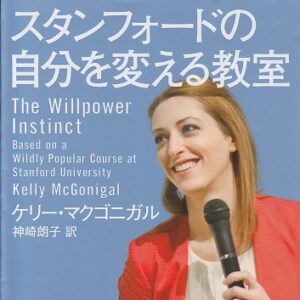2019.01.11
中世・ルネサンスの音楽
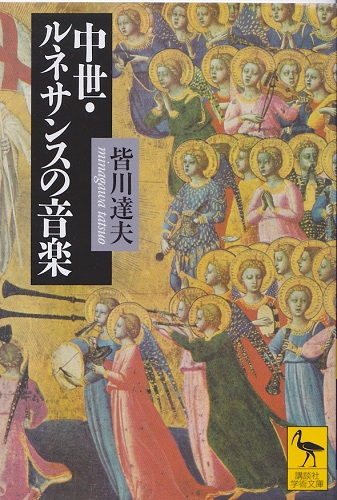
こんにちは。皆川達夫さんの著書「中世・ルネサンスの音楽」を読みました。学生時代に、確かに音楽史の講義で勉強したのだけれど、このあたりはみんなひとまとまりになってしまっていました。
改めて読んでみるといろいろ新しい知識を得ることができ、西洋音楽の流れについてなるほど、と思うことがありました。
日本と中世・ルネサンス音楽
西洋音楽は明治以降に取り入れられ、発展してきた、ということしか、私自身は認識していませんでした。
世界遺産に「長崎・天草の潜伏キリシタン関連遺産」が登録された時に、たまたま、皆川達夫さんの書かれたこの文章を読みました。
生月島のオラショ。年月を経て、日本的な節回しになっていても、奇跡的に原型が残っていたことに私はとても驚きました。それだけ大切に大切に守り続けていたものなのだということが伝わってきました。
そして、皆川さんの、元の聖歌をたどろうとする熱意。長年の研究の結果、蓄積されている知識の厚み。
そういうものがあったからこそ、元の聖歌にたどり着けたということに感動し、非常に印象に残っていました。
今回の、この本の最後の章に、日本とヨーロッパの音楽のつながりが書かれていて、オラショとグレゴリオ聖歌のことが書かれていました。
そればかりではなく、日本の箏曲、八橋検校の「六段の調べ」との関連の可能性についても述べられていました。
音楽が人の心の深いところを動かすからこそ、残っていく「何か」があるのかもしれません。
ギョーム・デュファイについて
確かにこの人物についても「勉強した」ような気がします。でも、内容は覚えていませんでしたし、実際にどんな曲があったか、全部忘れていました。
バッハと比較して述べている内容を読んで、時代の節目にはこういう人物が現れ、次の時代の扉を開くのだ、ということを改めて思いました。
このようにして、それまでフランス、イタリア、イギリスなどで、それぞれ独自の展開をみせていたもろもろの音楽技法が、ブルゴーニュおよびその属領のフランドルで、総合化、国際化をみせることになった。その総合化の仕事を、もっとも著しく、もっとも精力的に果たしたのが、ギョーム・デュファイであった。
彼は、その後のモンテヴェルディあるいはバッハと同じく、前の時代のもろもろの音楽技法を彼一身のうちに摂取し、同化し総合し、しかもその作品のすべてに彼自身の強烈な個性をきざみこんでいった、巨人的なスケールの作曲家であった。
皆川達夫 中世・ルネサンスの音楽 第五章 ルネサンス音楽を作った作曲家たち p.135
聞いてみたのですが、残念ながら、その前後の音楽をしっかり把握しているわけではないので、「同化・総合・個性」をはっきり感じ取れたわけではありません。
ただ、それまでのグレゴリオ聖歌と違い、3度の響きが多く聞こえ、そうするとずいぶん今につながる響きになる、という印象は残りました。
ヨーロッパというまとまり
全体を通して、強く感じたのは、ヨーロッパという陸続き(イギリスは島国ですが)の地域のまとまりの強さ、つながりの深さです。
例えば、フランドル楽派の人々は今のベルギー・フランスからヨーロッパ各地に行って活躍し、故郷に戻ってくる。
王室どうしの結婚によって、宮廷の文化も移動していき、影響しあっている。
このあたりは、日本という島国で生活している日本人の感覚とは大きく違うのかもしれません。
その中で、音楽も混じり合い、結果的に発展していったのだ、ということがとても良くわかりました。
皆川達夫さんには、「バロック音楽」という著作もあるので、続いて読んでいこうと思います。今度は鍵盤楽器もきっともっとたくさん取り上げられているでしょうから、よりピアノにつながるさまざまな学びがあると思います。